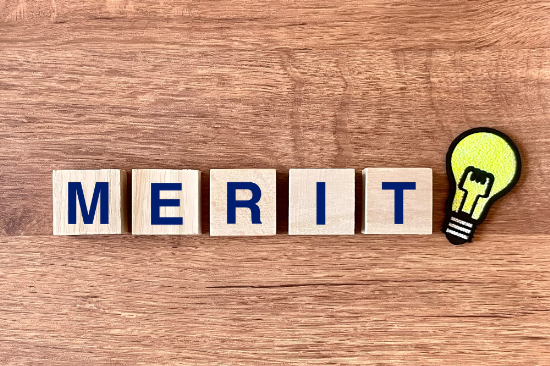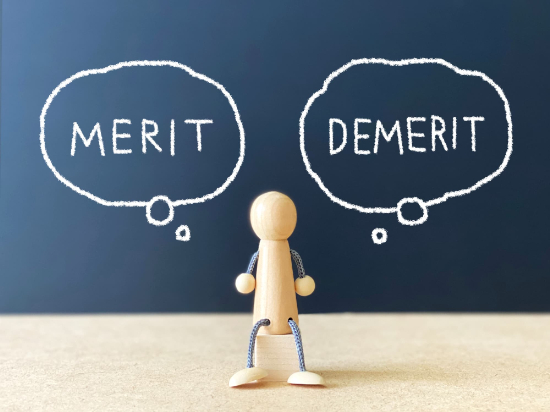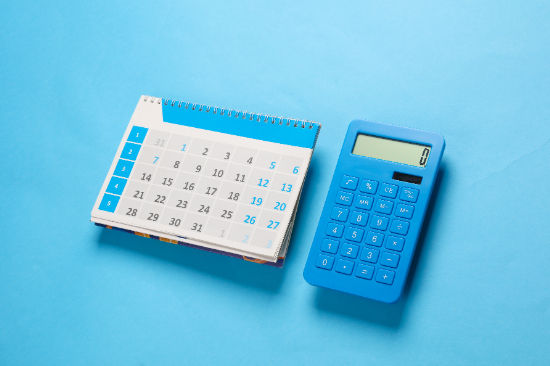こんにちは。横浜市緑区にある歯医者「礒部歯科医院」です。

マイオブレースは、成長期の子どもを対象にした矯正装置で、不正咬合の根本的な原因を改善して、顎が正しく成長するように促すことを目的としています。
小児矯正を検討されている方のなかには、歯科医院でマイオブレースでの治療をすすめられたという方もいるのではないでしょうか。
本記事では、マイオブレースとはどのような矯正装置か詳しく解説します。効果や治療の流れ、費用、期間についても詳しく解説しますので、マイオブレースでの治療を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
マイオブレースとは

マイオブレースとは、子どもの矯正治療に使用される矯正装置です。主に成長期の子どもを対象としており、舌の正しい使い方を習得したり、口呼吸を改善したりすることで、顎が正しく成長するように促すことを目的としています。
一般的なワイヤー矯正とは異なり、取り外しができるのが特徴です。装置は就寝中と日中1~2時間ほど装着します。自宅にいるときにだけ装置を装着すればよいため、お子さんへの負担を軽減しながら治療を進められるでしょう。
また、成長期のあごの発育をサポートするため、抜歯を避けられる可能性が高い点もメリットです。マイオブレースでの治療を検討する際は、歯科医院を受診して適応症か確認してもらう必要があります。
マイオブレースの効果

マイオブレースを使用した治療にはさまざまな効果があります。以下に、マイオブレースの効果について解説します。
歯並びの改善
マイオブレースを装着することで、永久歯が正しい位置に生えるよう、あごの成長をサポートします。マイオブレースを装着し、口周りの筋肉を鍛えることで、自然に歯並びが整うことが期待できるでしょう。
その結果、ワイヤー矯正や抜歯矯正を必要としないケースも多く見られます。
口呼吸の改善
マイオブレースには、口呼吸から鼻呼吸への切り替えを促す効果もあります。口呼吸になると舌の位置が下がるため、歯並びやあごの発育に悪影響を与えるだけでなく、睡眠の質や免疫力の低下にもつながるでしょう。
マイオブレースを装着することで、正しい呼吸法を習得できるため、口呼吸が改善され全身の健康にもよい影響を与えます。
あごの発育をサポート
成長期のあごは柔軟で、外部からの刺激に反応しやすい状態です。
マイオブレースを装着し、口周りの筋肉のバランスを整えることで、あごの発育をサポートし、将来的な歯並びや噛み合わせのトラブルを予防します。また、正常にあごが成長することで発音や咀嚼機能の向上も期待できるでしょう。
悪習癖の改善
マイオブレースには、歯並びに影響を与える悪習癖を改善する効果もあります。例えば、舌が正しい位置に置かれておらず、下がっていると、歯並びに影響を及ぼすことがあります。
舌を正しい位置に置くことは、きれいな歯並び・噛み合わせを保つためには必要不可欠です。マイオブレースを装着し、舌や口周りの筋肉を鍛えることで、正しい舌の位置を習得する効果が期待できるでしょう。
マイオブレースのメリット・デメリット
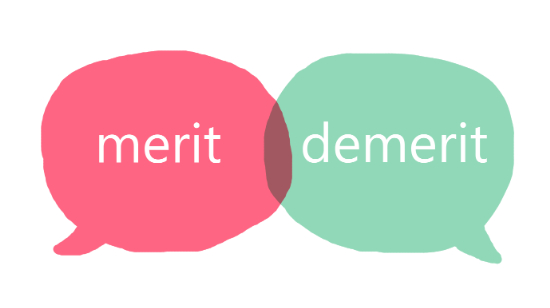
マイオブレースにはメリットだけでなくデメリットもあります。以下に、マイオブレースのメリットとデメリットについて詳しく解説します。
マイオブレースのメリット
マイオブレースのメリットは、以下の通りです。
抜歯のリスクを軽減できる
マイオブレースは、子どもの成長期にあごの発育を促進し、永久歯が並ぶスペースを確保します。これによって、歯を抜かずに歯並びが整う可能性が高まるでしょう。小さなうちに治療を始めることで、抜歯をせずに適切な歯並びが形成されることが期待できます。
痛みが少ない
痛みが少ないという点もマイオブレースのメリットです。ワイヤー矯正では、歯に装着した装置に力を加えて歯を動かします。そのため、ワイヤーを調整した直後や、歯が動くときに痛みが生じることがあるのです。
一方、マイオブレースでは、歯に力を加えて動かすことはしません。正常なあごの成長を促したり、歯並びに影響を及ぼす悪い癖を改善したりすることで、間接的に歯並びを整えます。そのため、治療中の痛みが少ないのです。
痛みが少ないという点は、小さなお子様にとって大きなメリットといえるでしょう。
後戻りを起こしにくい
後戻りを起こしにくいのもマイオブレースのメリットのひとつです。後戻りとは、矯正治療で整えた歯が元の位置に戻ろうと動くことです。
マイオブレースは歯を動かして歯並びを整えるものではありません。口周りの筋肉のバランスを整え、歯並びに影響を及ぼす原因にアプローチすることで、間接的に歯並びが整うように促すものです。
マイオブレースを使用することで、口周りの悪習癖を改善し、あごが正しく成長するように促すことができれば、矯正治療後に後戻りが起こりにくくなるでしょう。
全身の健康に良い影響がある
マイオブレースで口呼吸が改善されると、睡眠の質が上がり、日中の集中力や免疫力の向上が期待できます。また、噛み合わせが改善されると、食事がスムーズになり消化機能や栄養吸収が効率的になることもメリットといえるでしょう。
マイオブレースは、歯並びだけでなく全身の健康にも良い影響を与えます。
マイオブレースのデメリット
マイオブレースにはデメリットも存在します。以下に、マイオブレースのデメリットについて解説します。
効果が出るまで時間がかかる場合がある
マイオブレースを使用した治療は、口腔の悪習癖などを改善しながら自然な歯列を形成する治療のため、効果が現れるまでに時間がかかることがあります。正しい呼吸の仕方や舌の位置を習得するためには時間がかかる場合があるのです。
鼻呼吸や正しい呼吸の仕方を定着させるためには、患者さんの協力が欠かせません。治療期間が長引くこともあるため、忍耐強く取り組む必要があります。
使用時間を守る必要がある
マイオブレースは、日中の1〜2時間と就寝時に装着する必要があります。装着時間を守らないと、十分な効果が得られない場合があります。
小さな子どもの場合、装着を嫌がったり忘れたりすることがあるため、装着時間が課題になるケースも少なくありません。保護者の方のサポートが欠かせないため、負担に感じる方もいるでしょう。
適応範囲が限られている
マイオブレースは、軽度から中程度の不正咬合や歯並びの問題に対応できますが、重度のケースでは対応が難しいことがあります。骨格に大きな問題がある場合や、すでに歯並びが著しく乱れている場合には、ワイヤー矯正やほかの治療法が適応となる可能性もあるでしょう。
費用が高額
マイオブレースを使用した治療は、自由診療になるため決して安いとはいえません。全額自己負担となることが一般的なので費用面での負担が治療を開始する際の課題になることもあるでしょう。
違和感を覚えることがある
初めてマイオブレースを装着するときに、一時的に違和感を覚えることがあります。装着を継続することで次第に慣れることがほとんどですが、敏感な子どもにはストレスとなる可能性があるため注意が必要です。
お子さんの協力が必要
マイオブレースを使用した治療では、お子さんの協力が必要です。装置の装着を怠ると、効果が薄れる可能性があります。治療を成功させるためにはお子さんや保護者の方のモチベーション維持が重要となるでしょう。
マイオブレースの流れ

マイオブレースの治療はどのような流れでおこなわれるのか、気になる方もいるでしょう。以下に、マイオブレースの一般的な治療の流れを解説します。
カウンセリングと精密検査
まずはカウンセリングを行い、現在の歯並びやお口の中で気になることなどをうかがいます。矯正治療に関する疑問点や不安点がある場合は、カウンセリングの際に相談すると良いでしょう。
その後、精密検査をして口腔内の状態を確認します。この際、歯型の採取やレントゲン撮影、口腔内写真の撮影などをすることが一般的です。精密検査の結果をもとに歯科医師が治療計画を立てます。
装置の着脱法や使用方法の指導
マイオブレースは取り外し式なので、自己管理が必要です。自宅でしっかりと管理できるように使い方や装着時間について詳しい指導をおこないます。通常、日中の1〜2時間と就寝時に装着します。
悪習癖がある場合は、正しい呼吸法や舌の位置、飲み込み方を改善するためのトレーニングも並行しておこないます。
定期チェック
治療中は、定期的に歯科医院を受診して装置の適合状態や歯並び・噛み合わせの状態を確認します。必要に応じて装置の調整をおこなって、新しいトレーニング方法が追加されることもあるでしょう。
治療完了・定期検診
お口周りの筋肉のバランスが整い、口腔習慣の改善がみられたらマイオブレースを使用した治療は完了です。
治療後は、お口の中の状態を維持するためのフォローが必要です。定期検診で歯並び・噛み合わせを確認することで、治療後も安定した状態を保つことができるでしょう。
マイオブレースの費用と期間

マイオブレースをはじめ矯正治療は保険適用外の自由診療になります。そのため、高額な費用がかかります。マイオブレースを使用した治療にかかる費用は、一般的に30万〜40万円程度です。費用には、装置費用やトレーニング指導料が含まれているケースが多いでしょう。
歯科医院によって費用は異なるため、複数の歯科医院でカウンセリングを受けて比較検討することを推奨します。また、分割払いに対応している歯科医院も増えているので、一括での支払いが難しい方は分割払いに対応しているところを選択すると良いでしょう。
治療期間は通常1年半〜3年程度で、個々の歯並びの状態や装置の装着時間、生活習慣などによって左右されます。
マイオブレースを使用した治療は、早い段階で始めたほうが短期間で効果を得られる可能性が高いといわれています。具体的な費用や治療期間については歯科医院で確認してください。
まとめ

マイオブレースとは、歯並びに影響を及ぼす悪い癖や習慣を改善し、お口周りの筋肉のバランスを整えるために使用される装置です。取り外し可能でお子さんへの負担が少なく、不正咬合の原因を根本から改善できます。
費用は30万円〜40万円ほど、治療期間は1年半〜3年程度が目安です。費用や治療期間は、個々のお口の中の状態や習慣によって異なるため、事前に歯科医院で確認しましょう。
マイオブレースを使用した治療は早めに開始することが効果的だといわれています。気になる方は、カウンセリングを受けて検討してみてはいかがでしょうか。
小児矯正を検討されている方は、横浜市緑区にある歯医者「礒部歯科医院」にお気軽にご相談ください。
当院は、虫歯・歯周病治療、インプラント、小児歯科、ホワイトニングなど、さまざまな診療に力を入れています。診療案内ページはこちら、ネット診療予約も受け付けておりますので、ぜひご活用ください。
日付: 2025年1月22日 カテゴリ:歯のコラム and tagged マイオブレース, 小児矯正